ご近所付き合い&方言集

温かいご近所づきあいと助け合い
会津若松市の暮らし方
500以上の町内会が支える、
会津若松市のコミュニティ文化
会津若松市には500を超える町内会があり、各地域で共同の清掃活動や祭礼などの地域行事が盛んに行われています。これらの活動は、地域の環境を守るだけでなく、住民同士が交流する場にもなっており、新しく移り住んできた方も自然と地域に溶け込めるような温かい雰囲気が漂っています。祭礼では地域の歴史や伝統文化を体験できる機会も多く、参加することで会津の風土に親しむことができます。
ご近所同士のつながりが深まれば、季節の野菜をおすそ分けしてもらったり、いざというときには助け合える関係が築けます。冬の雪かきや災害時の支援など、日常生活の中での助け合いも自然と行われており、会津ならではのあたたかなコミュニティが広がっています。「会津の三泣き」と言われるように、会津の人々は初めは少し頑固で取っ付きにくいと感じるかもしれません。しかし、彼らは人とのつながりを何よりも大切にする心の温かい人が多く、一度信頼関係を築くと深い絆で結ばれます。そんな会津の人々との交流は、都会ではなかなか味わえない、地域に根ざした豊かな人間関係を育むきっかけになるでしょう。



十日市の風物詩「会津風車」
会津の十日市で見られる色とりどりの風車「会津風車」は、約400年の歴史を持つ縁起物の民芸品です。竹と紙で作られ、「一年中まめに働けますように」との願いを込めて神棚に飾られます。鮮やかな色合いと素朴な作りには、雪国の人々の春を待ちわびる思いが込められています。
「会津の三泣き」とは
会津人の性格を表す言葉があります。
「会津に来たときはその閉鎖的な人間関係に泣き、なじんでくると人情の深さに泣き、去るときは会津人の人情が忘れ難く泣く」というもので、会津人の気質がよく表されています。会津に来られると、はじめはとっつきにくい印象を会津の人に対してお持ちになるかもしれません。でも、会津で暮らしていくうちに会津人のあたたかさに触れることができるはずです。
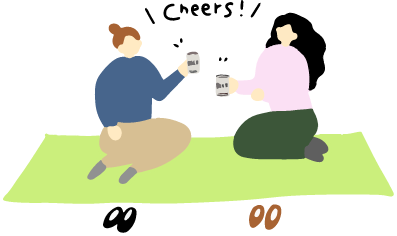
温かみと個性を感じる、会津若松の方言の魅力。

会津若松の暮らしが楽しくなる!
方言を知って地元との距離を縮めよう
会津若松市を含む会津地方では、地域独特の温かみや個性を感じさせる方言が日常会話で多く使われています。会津の方言には、昔ながらの表現や独特の響きがあり、他の地域の日本語とは一味違った趣があります。言葉自体に親しみが込められていることが多く、会津の人々の人柄や土地柄を表すものとして長年にわたって大切にされています。
■ おめさん
・「あなた」という意味。親しみを込めて相手を指す際に使います。
■ いがった
・「良かった」という意味。「いが」は「良い」を意味します。
■ あんべわりい
・「体調が悪い」や「具合が悪い」という意味で使われます。
■ めんごい
・「かわいい」という意味で、動物や子どもを褒めるときによく使います。
■ けっぱる
・「頑張る」という意味。「今日はけっぱって仕事するぞ!」といった具合に使います。
- 個人情報の取り扱いについて
- サイトマップ
- ©︎ 会津若松市定住・二地域居住推進協議会

